昆虫図鑑
数千種類の昆虫が棲み、箕面山(大阪)、貴船山(京都)と並び日本三大昆虫生息地に数えられる高尾山は、その種の多様さと都心からのアクセスの良さも重なって、古くから昆虫研究のフィールドとして愛されてきました。こうした経緯から、高尾山で初めて発見された種も多く、タカオシャチホコやタカオメダカカミキリなど、高尾山の名を冠に持つ昆虫も存在しています。
-
アカハナカミキリ カミキリムシ科

 アカハナカミキリ カミキリムシ科
アカハナカミキリ カミキリムシ科 北海道、本州、四国、九州、沖縄と、利尻島などに分布。平地から山地の林の中などに生息する。名前のとおり、頭部を除く全身が褐色がかった赤い色をしている。高尾山には比較的多く生息しており、目立つ体色なので見つけやすい。まれに胸部が黒いものもいる。触角は体長よりも短く、先の方がノコギリ状になっている。真夏に姿をみせ、野原や雑木林などを飛んで移動し、シシウドやノリウツギなどの花にとまり、花粉や蜜を食べる。幼虫はエゾマツ、アカトドマツなどの針葉樹の枯木や倒木、伐採された木を食べる。
北海道、本州、四国、九州、沖縄と、利尻島などに分布。平地から山地の林の中などに生息する。名前のとおり、頭部を除く全身が褐色がかった赤い色をしている。高尾山には比較的多く生息しており、目立つ体色なので見つけやすい。まれに胸部が黒いものもいる。触角は体長よりも短く、先の方がノコギリ状になっている。真夏に姿をみせ、野原や雑木林などを飛んで移動し、シシウドやノリウツギなどの花にとまり、花粉や蜜を食べる。幼虫はエゾマツ、アカトドマツなどの針葉樹の枯木や倒木、伐採された木を食べる。
体長|約12~22ミリ
成虫の出現期|7~9月頃 -
キマダラミヤマカミキリ カミキリムシ科

 キマダラミヤマカミキリ カミキリムシ科
キマダラミヤマカミキリ カミキリムシ科 本州、四国、九州と、佐渡、隠岐、対馬、屋久島などの島に分布。平地から山地の樹林や雑木林などに生息する。体全体が黄金色の微毛でおおわれていて、ビロードのように角度によって色や模様が変わって見える。胸部背面に円錐状(えんすいじょう)の突起がある。5月ごろから姿を見せ、夜行性で日中は樹上や落ち葉の下などに隠れていることが多い。日没後から活動をはじめ、樹液を求めてクヌギ、コナラ、クリなどの木に飛来する。灯火に集まることも多い。メスはクリやクヌギなどの朽ち木(くちき)に卵を産みつける。ふ化した幼虫はそれらの木材の部分を食べて成長する。
本州、四国、九州と、佐渡、隠岐、対馬、屋久島などの島に分布。平地から山地の樹林や雑木林などに生息する。体全体が黄金色の微毛でおおわれていて、ビロードのように角度によって色や模様が変わって見える。胸部背面に円錐状(えんすいじょう)の突起がある。5月ごろから姿を見せ、夜行性で日中は樹上や落ち葉の下などに隠れていることが多い。日没後から活動をはじめ、樹液を求めてクヌギ、コナラ、クリなどの木に飛来する。灯火に集まることも多い。メスはクリやクヌギなどの朽ち木(くちき)に卵を産みつける。ふ化した幼虫はそれらの木材の部分を食べて成長する。
体長|約22~35ミリ
成虫の出現期|5~8月頃 -
ルリボシカミキリ カミキリムシ科

 ルリボシカミキリ カミキリムシ科
ルリボシカミキリ カミキリムシ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地の樹林や雑木林などに生息する。名前のとおり青みの強い水色の体に大きな三対の黒斑が並ぶ、美しいカミキリムシとして知られる。この黒斑は左右のものがつながっていることもある。触角も青く節目に黒い毛の房がある。6月頃から姿を見せはじめ、日中に活動する。高尾山ではイヌブナの倒木によく見られ、コナラなどの樹液や、リョウブなどの花にも集まることがある。幼虫も成虫と同じブナ類などの木の内部を食べて成長する。
北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地の樹林や雑木林などに生息する。名前のとおり青みの強い水色の体に大きな三対の黒斑が並ぶ、美しいカミキリムシとして知られる。この黒斑は左右のものがつながっていることもある。触角も青く節目に黒い毛の房がある。6月頃から姿を見せはじめ、日中に活動する。高尾山ではイヌブナの倒木によく見られ、コナラなどの樹液や、リョウブなどの花にも集まることがある。幼虫も成虫と同じブナ類などの木の内部を食べて成長する。
体長|約18~30ミリ
成虫の出現期|6~9月頃 -
ミドリカミキリ カミキリムシ科

 ミドリカミキリ カミキリムシ科
ミドリカミキリ カミキリムシ科 北海道、本州、四国、九州と、礼文島、対馬、隠岐、屋久島などの島に分布。平地から山地の樹林や雑木林に生息する。体は長細く、名前のとおり全体が金属的な光沢のある緑色をしているが、角度によっては赤みがかって見えることもある。胸部の側面には小さな突起が一対ある。後ろ脚が異様に長く、その長さは体長以上にもなる。適度に草木が茂った、日当たりのいい雑木林の周囲でよくみられ、ガマズミやウツギ、クリなどの花の蜜を食べる。幼虫はクリ、クヌギ、コナラなどの木の内部を食べる。オスはメスと交尾したあと、メスが産卵するまで、ほかのオスに交尾されないよう付き添う習性を持つ。
北海道、本州、四国、九州と、礼文島、対馬、隠岐、屋久島などの島に分布。平地から山地の樹林や雑木林に生息する。体は長細く、名前のとおり全体が金属的な光沢のある緑色をしているが、角度によっては赤みがかって見えることもある。胸部の側面には小さな突起が一対ある。後ろ脚が異様に長く、その長さは体長以上にもなる。適度に草木が茂った、日当たりのいい雑木林の周囲でよくみられ、ガマズミやウツギ、クリなどの花の蜜を食べる。幼虫はクリ、クヌギ、コナラなどの木の内部を食べる。オスはメスと交尾したあと、メスが産卵するまで、ほかのオスに交尾されないよう付き添う習性を持つ。
体長|約15~21ミリ
季節|5~8月頃 -
ベニカミキリ カミキリムシ科

 ベニカミキリ カミキリムシ科
ベニカミキリ カミキリムシ科 北海道、本州、四国、九州と、佐渡、隠岐、対馬などの島に分布。平地から低山地の雑木林や緑地に生息する。名前のとおりに胸部と上翅(じょうし:甲虫類の二対の翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)は鮮やかな紅色で、胸部には黒い班点が並ぶ。頭部と触角、脚は黒い。オスは触角が体長よりも長く、メスは体長とほぼ同じ長さなので、容易に判別できる。よく似たヘリグロベニカミキリは上翅の後方に一対の黒い点があることで見分けられる。春先から姿を現し、ネギ、クリ、ハゼノキなどの花の蜜を食べる。幼虫はモウソウチクやマダケなどの枯れた竹材を食べるので、人家の竹垣などから羽化した成虫が出てくることもある。
北海道、本州、四国、九州と、佐渡、隠岐、対馬などの島に分布。平地から低山地の雑木林や緑地に生息する。名前のとおりに胸部と上翅(じょうし:甲虫類の二対の翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)は鮮やかな紅色で、胸部には黒い班点が並ぶ。頭部と触角、脚は黒い。オスは触角が体長よりも長く、メスは体長とほぼ同じ長さなので、容易に判別できる。よく似たヘリグロベニカミキリは上翅の後方に一対の黒い点があることで見分けられる。春先から姿を現し、ネギ、クリ、ハゼノキなどの花の蜜を食べる。幼虫はモウソウチクやマダケなどの枯れた竹材を食べるので、人家の竹垣などから羽化した成虫が出てくることもある。
体長|約13~17ミリ
季節|4~8月頃 -
アカジマトラカミキリ カミキリムシ科

 アカジマトラカミキリ カミキリムシ科
アカジマトラカミキリ カミキリムシ科 本州、四国、九州に分布。平地から山地の樹林や緑地に生息する。名前のとおり、赤いしま模様を持つトラカミキリの仲間。
本州、四国、九州に分布。平地から山地の樹林や緑地に生息する。名前のとおり、赤いしま模様を持つトラカミキリの仲間。
赤い部分は鮮紅色からオレンジ、ややピンクに近いものまで差がある。体長2センチに満たない小さなカミキリムシだが、体に対して触角や脚が太く、がっしりした体型に感じられる。似たような模様を持つカミキリも多いが、アカジマトラカミキリはその色彩で容易に判別がつく。成虫はケヤキなどの伐採木や大木の樹皮、イタドリ、ノリウツギなどの花の蜜を食べる。幼虫はエノキ、エゾエノキ、マメガキなどの木材の部分を食べて育つ。
体長|約13~17ミリ
季節|8~10月頃 -
シロトラカミキリ カミキリムシ科

 シロトラカミキリ カミキリムシ科
シロトラカミキリ カミキリムシ科 北海道、本州、四国、九州と、利尻、佐渡、隠岐、対馬などの島に分布。平地から山地の樹林や草地などに生息している。その名のとおり、地色はほとんど白に近い。似たような色のトラカミキリの仲間はほかにもいるが、シロトラカミキリは黒い模様が背面中央部に入らないことで区別できる。1センチを少し超えるほどの小型のカミキリムシで、姿を見せはじめるのは5月上旬頃から。日中に草木の生い茂る緑地を飛びまわり、クリ、カエデ類、ノリウツギなどの花にとまって花粉や蜜を食べる。メスはブナ、シラカシ、ケヤキなどの植物の枯木や伐採木などに卵を産みつけ、幼虫はこれらの朽ち木(くちき)のなかで木の内部を食べて育つ。
北海道、本州、四国、九州と、利尻、佐渡、隠岐、対馬などの島に分布。平地から山地の樹林や草地などに生息している。その名のとおり、地色はほとんど白に近い。似たような色のトラカミキリの仲間はほかにもいるが、シロトラカミキリは黒い模様が背面中央部に入らないことで区別できる。1センチを少し超えるほどの小型のカミキリムシで、姿を見せはじめるのは5月上旬頃から。日中に草木の生い茂る緑地を飛びまわり、クリ、カエデ類、ノリウツギなどの花にとまって花粉や蜜を食べる。メスはブナ、シラカシ、ケヤキなどの植物の枯木や伐採木などに卵を産みつけ、幼虫はこれらの朽ち木(くちき)のなかで木の内部を食べて育つ。
体長|約10~16ミリ
成虫の出現期|5~8月頃 -
ゴマダラカミキリ カミキリムシ科

 ゴマダラカミキリ カミキリムシ科
ゴマダラカミキリ カミキリムシ科 北海道、本州、四国、九州、沖縄と、佐渡、隠岐、対馬、種子島、屋久島などの島に分布。低地から山地の雑木林などに生息する。成虫・幼虫ともにヤナギ類、シイ類、ミカン類、カエデ類など幅広い食性を持ち、畑地などにも多いことから、もっともよく知られるカミキリムシのひとつ。高尾山でも登山道でよく見かけられる。光沢のある黒色の体には白い斑点が散らばる。触角は水色と黒のしま模様になっていて、オスは体長の2倍近くになるが、メスは体長1.2倍ほど。しばしば庭木、街路樹などを枯死させる被害を与えることがある。
北海道、本州、四国、九州、沖縄と、佐渡、隠岐、対馬、種子島、屋久島などの島に分布。低地から山地の雑木林などに生息する。成虫・幼虫ともにヤナギ類、シイ類、ミカン類、カエデ類など幅広い食性を持ち、畑地などにも多いことから、もっともよく知られるカミキリムシのひとつ。高尾山でも登山道でよく見かけられる。光沢のある黒色の体には白い斑点が散らばる。触角は水色と黒のしま模様になっていて、オスは体長の2倍近くになるが、メスは体長1.2倍ほど。しばしば庭木、街路樹などを枯死させる被害を与えることがある。
体長|約25~35ミリ
成虫の出現期|6~8月頃 -
キボシカミキリ カミキリムシ科

 キボシカミキリ カミキリムシ科
キボシカミキリ カミキリムシ科 本州、四国、九州と、隠岐、壱岐、対馬などの島に分布。平地から低山地の森林に生息するが、農耕地や市街地の街路樹などでも見かけられる。長い触角を持つカミキリムシで、オスは体長の3倍近くにもなる。体色は黒で黄白色から黄色の斑点が散らばることが多い。初夏から秋口にかけて姿を現し、イチジク、クワ、ミカン類などの木の葉や樹皮を強力なアゴでかじりながら食べる。灯火にもよく集まる。メスはこれらの木に傷をつけ、そこに卵を産みつける。ふ化した幼虫は木材を食べながら成長する。
本州、四国、九州と、隠岐、壱岐、対馬などの島に分布。平地から低山地の森林に生息するが、農耕地や市街地の街路樹などでも見かけられる。長い触角を持つカミキリムシで、オスは体長の3倍近くにもなる。体色は黒で黄白色から黄色の斑点が散らばることが多い。初夏から秋口にかけて姿を現し、イチジク、クワ、ミカン類などの木の葉や樹皮を強力なアゴでかじりながら食べる。灯火にもよく集まる。メスはこれらの木に傷をつけ、そこに卵を産みつける。ふ化した幼虫は木材を食べながら成長する。
体長|約14~30ミリ
成虫の出現期|5~11月頃 -
ヤツメカミキリ カミキリムシ科

 ヤツメカミキリ カミキリムシ科
ヤツメカミキリ カミキリムシ科 北海道、本州、四国、九州と、佐渡、隠岐、対馬、種子島、屋久島などの島に分布。平地から山地の森林や緑地に生息する。体表は微毛におおわれており、この毛の色が異なることで、黄色から青緑色までの変異がある。上翅(じょうし:甲虫類の二対の翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)の外縁に沿って8つの黒い斑点が並び、これが名前の由来となっている。他に頭部に2つ、胸部に4つの規則的な黒い斑点があるが、これは食樹となるウメやサクラの樹皮に着生するウメノキゴケへの擬態(ほかのものの様子や姿に似せること)といわれる。初夏を迎えるころから姿を現わし、オオヤマザクラ、ウメ、ソメイヨシノ、シナノキなどの老木、枯木、朽ち木(くちき)に集まって樹皮などを食べる。灯火に飛来してくることも多い。幼虫も成虫と同じくサクラなどの木の内部を食べる。
北海道、本州、四国、九州と、佐渡、隠岐、対馬、種子島、屋久島などの島に分布。平地から山地の森林や緑地に生息する。体表は微毛におおわれており、この毛の色が異なることで、黄色から青緑色までの変異がある。上翅(じょうし:甲虫類の二対の翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)の外縁に沿って8つの黒い斑点が並び、これが名前の由来となっている。他に頭部に2つ、胸部に4つの規則的な黒い斑点があるが、これは食樹となるウメやサクラの樹皮に着生するウメノキゴケへの擬態(ほかのものの様子や姿に似せること)といわれる。初夏を迎えるころから姿を現わし、オオヤマザクラ、ウメ、ソメイヨシノ、シナノキなどの老木、枯木、朽ち木(くちき)に集まって樹皮などを食べる。灯火に飛来してくることも多い。幼虫も成虫と同じくサクラなどの木の内部を食べる。
体長|約10~18ミリ
成虫の出現期|5~7月頃 -
ラミーカミキリ カミキリムシ科

 ラミーカミキリ カミキリムシ科
ラミーカミキリ カミキリムシ科 関東より西の本州、四国、九州と、対馬、隠岐、種子島などの島に分布。平地から山地の雑木林やその周辺の緑地などに生息する。外来種で、江戸時代末期に中国から輸入された植物ラミー(イラクサ科)にくっついて、当時の貿易地の長崎県入ってきたといわれる。分布域が徐々に北上してきており、これは温暖化の影響とされている。体には白緑色の地色に大きな黒い斑点模様が入り、色合いが美しい。かつては高尾山にはいなかったが、1990年代の前半ごろから見られるようになり、今では5月から8月頃にもっともよく見かけるカミキリムシのひとつとなった。日中に活動し、飛びまわりながら餌となるラミー、カラムシ、ヤブマオ、シナノキ、ムクゲといった植物の葉や茎などを食べる。幼虫は成虫と同じ植物の茎や根を食べて成長する。
関東より西の本州、四国、九州と、対馬、隠岐、種子島などの島に分布。平地から山地の雑木林やその周辺の緑地などに生息する。外来種で、江戸時代末期に中国から輸入された植物ラミー(イラクサ科)にくっついて、当時の貿易地の長崎県入ってきたといわれる。分布域が徐々に北上してきており、これは温暖化の影響とされている。体には白緑色の地色に大きな黒い斑点模様が入り、色合いが美しい。かつては高尾山にはいなかったが、1990年代の前半ごろから見られるようになり、今では5月から8月頃にもっともよく見かけるカミキリムシのひとつとなった。日中に活動し、飛びまわりながら餌となるラミー、カラムシ、ヤブマオ、シナノキ、ムクゲといった植物の葉や茎などを食べる。幼虫は成虫と同じ植物の茎や根を食べて成長する。
体長|約10~20ミリ
成虫の出現期|5~8月頃 -
シロスジカミキリ カミキリムシ科

 シロスジカミキリ カミキリムシ科
シロスジカミキリ カミキリムシ科 本州、四国、九州と、佐渡、隠岐、対馬、奄美などの島々に分布。平地から山地の樹林や緑地に生息する。日本産のカミキリムシでは最大種となり、大きいものは体長が6センチ近くにもなる。体は黒く、全体が灰色の微毛におおわれている。上翅(じょうし:甲虫類の二対の翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)に大小の黄斑がすじ状に並んでいるが、この模様は標本などでは白くなってしまうことから命名の際に「白すじ」とされた。大きな 複眼(ふくがん:小さな眼が多数集まって、ひとつの大きな眼を形成したもの)とよく発達した大あごを持つ。どちらかというと夜行性だが、日中に活動することもある。雑木林に生えるヤナギ科、クルミ科、カバノキ科、ブナ科、ニレ科などの木の樹皮をかじって食べる。またそれらの木々の樹液にも集まる。幼虫はクリ、クヌギ、シイなどの木の内部を食べて育つ。
本州、四国、九州と、佐渡、隠岐、対馬、奄美などの島々に分布。平地から山地の樹林や緑地に生息する。日本産のカミキリムシでは最大種となり、大きいものは体長が6センチ近くにもなる。体は黒く、全体が灰色の微毛におおわれている。上翅(じょうし:甲虫類の二対の翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)に大小の黄斑がすじ状に並んでいるが、この模様は標本などでは白くなってしまうことから命名の際に「白すじ」とされた。大きな 複眼(ふくがん:小さな眼が多数集まって、ひとつの大きな眼を形成したもの)とよく発達した大あごを持つ。どちらかというと夜行性だが、日中に活動することもある。雑木林に生えるヤナギ科、クルミ科、カバノキ科、ブナ科、ニレ科などの木の樹皮をかじって食べる。またそれらの木々の樹液にも集まる。幼虫はクリ、クヌギ、シイなどの木の内部を食べて育つ。
体長|約45~55ミリ
季節|6~8月頃 -
ヒゲナガオトシブミ オトシブミ科

 ヒゲナガオトシブミ オトシブミ科
ヒゲナガオトシブミ オトシブミ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から低山地の雑木林や草むらなどに生息する。体色は地域や個体によってばらつきがあり、黄褐色に近いものもいるが、多くはつやのある赤褐色から暗褐色をしている。オスとメスで体型に違いがあり、オスは頭部と胸部がひじょうに細長く、名前のとおりに触角もとても長い独特の姿をしている。体もメスよりもオスの方が大きい。メスは胸部も触角もそれほど長くなく、別種のウスアカオトシブミに似る。姿を見られるのは初夏から真夏にかけてで、アブラチャン、コブシ、イタドリ、ケクロモジ、カナクギノキなどの葉に切れこみを入れ、卵をひとつ産んで、小さく折りたたみ、幼虫のための「ゆりかご」を作り、地面に落とす。オトシブミの名は、これを「落とし文(誰かに読ませるために地面に落とした手紙)」に見立てたもの。ふ化した幼虫は、ゆりかごとなった葉を食べて育つ。オトシブミの種類によっては、ゆりかごを落とさずに葉に残すものもいる。
北海道、本州、四国、九州に分布。平地から低山地の雑木林や草むらなどに生息する。体色は地域や個体によってばらつきがあり、黄褐色に近いものもいるが、多くはつやのある赤褐色から暗褐色をしている。オスとメスで体型に違いがあり、オスは頭部と胸部がひじょうに細長く、名前のとおりに触角もとても長い独特の姿をしている。体もメスよりもオスの方が大きい。メスは胸部も触角もそれほど長くなく、別種のウスアカオトシブミに似る。姿を見られるのは初夏から真夏にかけてで、アブラチャン、コブシ、イタドリ、ケクロモジ、カナクギノキなどの葉に切れこみを入れ、卵をひとつ産んで、小さく折りたたみ、幼虫のための「ゆりかご」を作り、地面に落とす。オトシブミの名は、これを「落とし文(誰かに読ませるために地面に落とした手紙)」に見立てたもの。ふ化した幼虫は、ゆりかごとなった葉を食べて育つ。オトシブミの種類によっては、ゆりかごを落とさずに葉に残すものもいる。
体長|約8~12ミリ
成虫の出現期|5~7月頃 -
ヒメシロコブゾウムシ ゾウムシ科

 ヒメシロコブゾウムシ ゾウムシ科
ヒメシロコブゾウムシ ゾウムシ科 本州、四国、九州、沖縄と、対馬、屋久島などに分布。平地から山地の雑木林やその周辺の緑地などに生息する。全身がほぼ灰白色だが、これは非常に細かい粉状のものでおおわれているためである。この粉ははがれやすく、徐々に背面の中央などに見える地色の部分が多くなってくる。上翅(じょうし:甲虫類の二対の 翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)は全体に小さな凹凸があり、名前のとおり、後方に1対のこぶ状の突起がある。よく似たシロコブゾウムシより、「ヒメ」の名のとおり、体も突起もやや小さい。姿を現わすのは春先から夏にかけて。ヤツデやウド、タラなどの葉を食べ、普段はそれらの植物の葉の上にいることが多い。
本州、四国、九州、沖縄と、対馬、屋久島などに分布。平地から山地の雑木林やその周辺の緑地などに生息する。全身がほぼ灰白色だが、これは非常に細かい粉状のものでおおわれているためである。この粉ははがれやすく、徐々に背面の中央などに見える地色の部分が多くなってくる。上翅(じょうし:甲虫類の二対の 翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)は全体に小さな凹凸があり、名前のとおり、後方に1対のこぶ状の突起がある。よく似たシロコブゾウムシより、「ヒメ」の名のとおり、体も突起もやや小さい。姿を現わすのは春先から夏にかけて。ヤツデやウド、タラなどの葉を食べ、普段はそれらの植物の葉の上にいることが多い。
体長|約11~14ミリ
成虫の出現期|4~7月頃 -
カツオゾウムシ ゾウムシ科

 カツオゾウムシ ゾウムシ科
カツオゾウムシ ゾウムシ科 北海道、本州、四国、九州と、対馬などに分布。平地から山地の雑木林や緑地などに生息する。ユニークな名前は、くびれのない流線型の細長い体型で、全体が赤褐色の粉におおわれており、あたかも「鰹節(かつおぶし)」のように見えることに由来する(なぜ「ぶし」が省略されているのかは不明)。粉が落ちた個体は地の色が出て黒っぽく見える。上翅 (じょうし:甲虫類の二対の翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)の後端は鋭角にとがっている。よく似た種類のハスジカツオゾウムシは上の翅に黒いV字型の模様があり、上の翅の後端の角度が広いことで区別できる。イタドリやミゾソバなどのタデ科植物の葉を食べ、それらの葉の上にいることが多い。幼虫は同じ植物の茎の内部を食べる。
北海道、本州、四国、九州と、対馬などに分布。平地から山地の雑木林や緑地などに生息する。ユニークな名前は、くびれのない流線型の細長い体型で、全体が赤褐色の粉におおわれており、あたかも「鰹節(かつおぶし)」のように見えることに由来する(なぜ「ぶし」が省略されているのかは不明)。粉が落ちた個体は地の色が出て黒っぽく見える。上翅 (じょうし:甲虫類の二対の翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)の後端は鋭角にとがっている。よく似た種類のハスジカツオゾウムシは上の翅に黒いV字型の模様があり、上の翅の後端の角度が広いことで区別できる。イタドリやミゾソバなどのタデ科植物の葉を食べ、それらの葉の上にいることが多い。幼虫は同じ植物の茎の内部を食べる。
体長|約10~12ミリ
成虫の出現期|5~8月頃 -
オジロアシナガゾウムシ ゾウムシ科

 オジロアシナガゾウムシ ゾウムシ科
オジロアシナガゾウムシ ゾウムシ科 本州、四国、九州に分布。平地から山地の林やその周辺の緑地、草原などに生息する。全体の地色は黒で、ところどころに 鱗毛(りんもう)という細かい毛が密生し、その部分が白くなっている。上翅(じょうし:甲虫類の二対の翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)の後部はほぼ白く、オジロの名はこれに由来する。アシナガゾウムシは分類上のグループ名で、本種ではそれほど脚の長さは目立たない。春先から姿を現わし、幼虫も成虫もクズを食べ、成虫はクズの葉の上でよく見ることができる。危険を察知すると脚をたたみ、死んだように動かなくなる習性がある。メスはクズの茎に傷をつけて卵を産み、ふ化した幼虫は茎の中身を食べて成長する。
本州、四国、九州に分布。平地から山地の林やその周辺の緑地、草原などに生息する。全体の地色は黒で、ところどころに 鱗毛(りんもう)という細かい毛が密生し、その部分が白くなっている。上翅(じょうし:甲虫類の二対の翅(はね)のうち、背部をおおうかたい翅)の後部はほぼ白く、オジロの名はこれに由来する。アシナガゾウムシは分類上のグループ名で、本種ではそれほど脚の長さは目立たない。春先から姿を現わし、幼虫も成虫もクズを食べ、成虫はクズの葉の上でよく見ることができる。危険を察知すると脚をたたみ、死んだように動かなくなる習性がある。メスはクズの茎に傷をつけて卵を産み、ふ化した幼虫は茎の中身を食べて成長する。
体長|約9~10ミリ
成虫の出現期|4~10月頃 -
オオゾウムシ オサゾウムシ科

 オオゾウムシ オサゾウムシ科
オオゾウムシ オサゾウムシ科 北海道、本州、四国、九州、沖縄と、伊豆大島、対馬などに分布。低地から山地の雑木林や森林に生息する。全身が茶褐色でところどころに黒い斑があるが、本来の地色は黒く、長生きしている個体ほど全体が黒っぽく見える。ごつごつした鋳物(いもの)のような体は非常にかたい。その名のとおり、ゾウの鼻のようにのびた口が目立つ。日本産のゾウムシの中では最大種。成虫がよく見られるのは初夏から真夏にかけてで、クヌギやコナラなどの木に集まり、樹液をなめる。昼間は倒木や朽ち木(くちき)などの下にいることが多い。成虫になってから2年ほど生きるとされている。卵は木の中に産みつけられ、幼虫は材部を深くまで食べ進む。
北海道、本州、四国、九州、沖縄と、伊豆大島、対馬などに分布。低地から山地の雑木林や森林に生息する。全身が茶褐色でところどころに黒い斑があるが、本来の地色は黒く、長生きしている個体ほど全体が黒っぽく見える。ごつごつした鋳物(いもの)のような体は非常にかたい。その名のとおり、ゾウの鼻のようにのびた口が目立つ。日本産のゾウムシの中では最大種。成虫がよく見られるのは初夏から真夏にかけてで、クヌギやコナラなどの木に集まり、樹液をなめる。昼間は倒木や朽ち木(くちき)などの下にいることが多い。成虫になってから2年ほど生きるとされている。卵は木の中に産みつけられ、幼虫は材部を深くまで食べ進む。
体長|約12~29ミリ
成虫の出現期|6~9月頃 -
オオスズメバチ スズメバチ科

 オオスズメバチ スズメバチ科
オオスズメバチ スズメバチ科 北海道、本州、四国、九州と、屋久島、種子島などに分布。平地から低山地に生息し、住宅街などでも活動する。日本産のハチの最大種で、濃いオレンジ色と黒のしま模様でよく目立つ。土の中などに巣を作り、そこをすみかとする。肉食性で、大型の昆虫を主な餌とするが、集団でほかのハチの巣を襲い、捕らえたさなぎや幼虫なども食べる。雑木林の樹液にもよく集まる。攻撃性の強いハチとしてよく知られ、人間を死に至らすほどの猛毒の持ち主。見かけたり、近くで「ブーン」という大きな羽音がしたら、慌てずにゆっくりとその場を離れる。甘いドリンク類や弁当に近づいてくることもある。
北海道、本州、四国、九州と、屋久島、種子島などに分布。平地から低山地に生息し、住宅街などでも活動する。日本産のハチの最大種で、濃いオレンジ色と黒のしま模様でよく目立つ。土の中などに巣を作り、そこをすみかとする。肉食性で、大型の昆虫を主な餌とするが、集団でほかのハチの巣を襲い、捕らえたさなぎや幼虫なども食べる。雑木林の樹液にもよく集まる。攻撃性の強いハチとしてよく知られ、人間を死に至らすほどの猛毒の持ち主。見かけたり、近くで「ブーン」という大きな羽音がしたら、慌てずにゆっくりとその場を離れる。甘いドリンク類や弁当に近づいてくることもある。
体長|約27~45ミリ
成虫の出現期|4~10月頃 -
キイロスズメバチ スズメバチ科

 キイロスズメバチ スズメバチ科
キイロスズメバチ スズメバチ科 本州、四国、九州と、佐渡、対馬、屋久島などの島に分布。低地から山地の木々の茂る里山や雑木林などに生息する。オオスズメバチよりもひとまわり小さい中型のスズメバチで働きバチは約20ミリ、オスが約20~24ミリ、女王バチは約25~28ミリになる。春先から姿をみせはじめ、樹木の洞や土の中などに球形の巣を作る。近年は都市部の人家の軒下や壁などにも作ることが多く、問題となっている。名前のとおり、体色は黄色みが強い。攻撃的な性格で少しの刺激でも襲ってくるので、巣を見かけても近寄ることのないよう気をつけたい。花の蜜や樹液などを好み、セミなど様々な昆虫も捕らえて餌にする。
本州、四国、九州と、佐渡、対馬、屋久島などの島に分布。低地から山地の木々の茂る里山や雑木林などに生息する。オオスズメバチよりもひとまわり小さい中型のスズメバチで働きバチは約20ミリ、オスが約20~24ミリ、女王バチは約25~28ミリになる。春先から姿をみせはじめ、樹木の洞や土の中などに球形の巣を作る。近年は都市部の人家の軒下や壁などにも作ることが多く、問題となっている。名前のとおり、体色は黄色みが強い。攻撃的な性格で少しの刺激でも襲ってくるので、巣を見かけても近寄ることのないよう気をつけたい。花の蜜や樹液などを好み、セミなど様々な昆虫も捕らえて餌にする。
体長|約20~28ミリ
成虫の出現期|4~11月頃 -
クロスズメバチ スズメバチ科

 クロスズメバチ スズメバチ科
クロスズメバチ スズメバチ科 北海道、本州、四国、九州と、佐渡島、対馬、屋久島などに分布。平地から山地の雑木林やその周辺の緑地に生息する。名前のとおり、体は光沢のある黒で、白い斑点模様と帯が入る。春の訪れとともに活動をはじめ、主に土の中に巣をつくるが、主な餌は昆虫やクモで、ガの幼虫などを好む。オオスズメバチやキイロスズメバチに比べると攻撃的でなく、毒性も弱いが、体質によってはショック症状を起こすこともあるので注意。「ジバチ」の別名でも広く知られており、長野県などでは幼虫やさなぎが「ハチの子」として食べられている。
北海道、本州、四国、九州と、佐渡島、対馬、屋久島などに分布。平地から山地の雑木林やその周辺の緑地に生息する。名前のとおり、体は光沢のある黒で、白い斑点模様と帯が入る。春の訪れとともに活動をはじめ、主に土の中に巣をつくるが、主な餌は昆虫やクモで、ガの幼虫などを好む。オオスズメバチやキイロスズメバチに比べると攻撃的でなく、毒性も弱いが、体質によってはショック症状を起こすこともあるので注意。「ジバチ」の別名でも広く知られており、長野県などでは幼虫やさなぎが「ハチの子」として食べられている。
体長|約10~16ミリ
成虫の出現期|3~11月頃 -
ムモンホソアシナガバチ スズメバチ科

 ムモンホソアシナガバチ スズメバチ科
ムモンホソアシナガバチ スズメバチ科 本州、四国、九州と、佐渡島、対馬、屋久島などに分布。平地から山地の林や、その周辺の緑地などに生息する。長い後ろ脚をたらして飛ぶアシナガバチの一種。よく似ているヒメホソアシナガバチとは、頭部に黒い模様がないことで区別でき、名前もそれにちなむ。春先から姿をみせはじめ、低木の葉や草の葉裏などに巣を作る。体色はやや褪せたような黄色で体中に淡褐色のまだら模様がはいる。細身で小型だが攻撃性は強く、最盛期の働きバチの数は100匹以上にもなるので、巣を見つけても近づかない。主な餌は昆虫で、ガの幼虫などを捕らえて食べる。
本州、四国、九州と、佐渡島、対馬、屋久島などに分布。平地から山地の林や、その周辺の緑地などに生息する。長い後ろ脚をたらして飛ぶアシナガバチの一種。よく似ているヒメホソアシナガバチとは、頭部に黒い模様がないことで区別でき、名前もそれにちなむ。春先から姿をみせはじめ、低木の葉や草の葉裏などに巣を作る。体色はやや褪せたような黄色で体中に淡褐色のまだら模様がはいる。細身で小型だが攻撃性は強く、最盛期の働きバチの数は100匹以上にもなるので、巣を見つけても近づかない。主な餌は昆虫で、ガの幼虫などを捕らえて食べる。
体長|約14~20ミリ
成虫の出現期|4~10月頃 -
クマバチ ミツバチ科

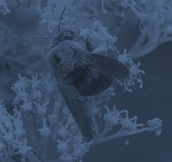 クマバチ ミツバチ科
クマバチ ミツバチ科 本州、四国、九州と、対馬、屋久島などに分布。平地から山地の雑木林やその周辺の緑地に生息し、人家の庭や公園などでもよく見られる。春先から初夏にかけて姿を見せはじめ、さまざまな花々をまわりながら、花粉や蜜を集めて餌にする。オスは山の尾根や野原などにそれぞれなわばりをもっており、ホバリング(一定の位置で飛び続けること)しながら同じ場所を見張っている姿を見かけることがある。潅木(かんぼく)や枯れ枝などに穴を掘って巣を作り、子供を育てる。羽の音が大きく、毛むくじゃらな姿であることから怖がられるが、実際はおとなしく攻撃してくることはほとんどない。
本州、四国、九州と、対馬、屋久島などに分布。平地から山地の雑木林やその周辺の緑地に生息し、人家の庭や公園などでもよく見られる。春先から初夏にかけて姿を見せはじめ、さまざまな花々をまわりながら、花粉や蜜を集めて餌にする。オスは山の尾根や野原などにそれぞれなわばりをもっており、ホバリング(一定の位置で飛び続けること)しながら同じ場所を見張っている姿を見かけることがある。潅木(かんぼく)や枯れ枝などに穴を掘って巣を作り、子供を育てる。羽の音が大きく、毛むくじゃらな姿であることから怖がられるが、実際はおとなしく攻撃してくることはほとんどない。
体長|約20~24ミリ
成虫の出現期|3~10月頃 -
ベッコウバチ ベッコウバチ科

 ベッコウバチ ベッコウバチ科
ベッコウバチ ベッコウバチ科 本州、四国、九州、沖縄に分布。クモを捕らえて幼虫の餌にする習性を持つハチの仲間で、生息する場所も林縁部や適度に木の生えている草地など、クモが多く生息する環境となる。ベッコウバチという名前は、やや赤みがかった黄色い体色をべっこう(タイマイというウミガメの甲ら)色にたとえたもの。単独で生活し、自分が棲むための巣は作らないが、幼虫のために地面に穴をほり、その中にクモを入れて卵を産みつける。卵からかえった幼虫はクモの体を食べて成長する。クモはハチの毒によって麻痺状態となって生きており、腐ったりすることはない。
本州、四国、九州、沖縄に分布。クモを捕らえて幼虫の餌にする習性を持つハチの仲間で、生息する場所も林縁部や適度に木の生えている草地など、クモが多く生息する環境となる。ベッコウバチという名前は、やや赤みがかった黄色い体色をべっこう(タイマイというウミガメの甲ら)色にたとえたもの。単独で生活し、自分が棲むための巣は作らないが、幼虫のために地面に穴をほり、その中にクモを入れて卵を産みつける。卵からかえった幼虫はクモの体を食べて成長する。クモはハチの毒によって麻痺状態となって生きており、腐ったりすることはない。
体長|約17~25ミリ
季節|7~9月頃 -
クロオオアリ アリ科

 クロオオアリ アリ科
クロオオアリ アリ科 北海道、本州、四国、九州と、対馬、屋久島などの島に分布。平地から山地の草地などに生息する。開けた地面に巣を作るので、都心部の公園や庭先などでもよく見られる。日本産アリでは最大種で、働きアリは約10ミリ、女王アリは約17ミリほどにもなる。体色は黒色で、腹部はやや褐色。地中に掘った巣の中で女王アリを中心とした集団生活を行なう。餌を探すのは働きアリの仕事で、単独もしくは数匹程度で行動し、死んだ虫や、アブラムシの分泌液などを餌にする。5月から6月頃、 翅(はね)をもったオスアリとメスアリは巣から飛び立ち、交尾を行なう。地上に降りるとメスアリは翅を落とし、新しい巣を作る。最初に生まれた何匹かはメスアリが世話をするが、それが働きアリになるとメスアリは卵を産むだけの女王アリとなる。
北海道、本州、四国、九州と、対馬、屋久島などの島に分布。平地から山地の草地などに生息する。開けた地面に巣を作るので、都心部の公園や庭先などでもよく見られる。日本産アリでは最大種で、働きアリは約10ミリ、女王アリは約17ミリほどにもなる。体色は黒色で、腹部はやや褐色。地中に掘った巣の中で女王アリを中心とした集団生活を行なう。餌を探すのは働きアリの仕事で、単独もしくは数匹程度で行動し、死んだ虫や、アブラムシの分泌液などを餌にする。5月から6月頃、 翅(はね)をもったオスアリとメスアリは巣から飛び立ち、交尾を行なう。地上に降りるとメスアリは翅を落とし、新しい巣を作る。最初に生まれた何匹かはメスアリが世話をするが、それが働きアリになるとメスアリは卵を産むだけの女王アリとなる。
体長|約7~13ミリ(働きアリ)
季節|4~11月頃 -
ムネアカオオアリ アリ科

 ムネアカオオアリ アリ科
ムネアカオオアリ アリ科 北海道、本州、四国、九州と、屋久島、対馬などに分布。平地から山地の林内や草地などに生息する。日本に分布するアリのなかではクロオオアリと並ぶ最大種で、女王アリは2センチ近くにもなる。頭部と脚は黒色で、胸部と腹部の前方付近が赤褐色をしているのが大きな特徴。中には胸部のみ赤褐色のものもいる。土の中ではなく、林の朽ち(くちき)や木の根元などに巣を作るので、都心部の公園などで見かけることはほとんどない。通常見かけるのは働きアリで、巣の外では基本的に単独で行動し、行列を作るようなことはほとんどない。小さな昆虫の死骸や、アブラムシの出す蜜などを餌にする。
北海道、本州、四国、九州と、屋久島、対馬などに分布。平地から山地の林内や草地などに生息する。日本に分布するアリのなかではクロオオアリと並ぶ最大種で、女王アリは2センチ近くにもなる。頭部と脚は黒色で、胸部と腹部の前方付近が赤褐色をしているのが大きな特徴。中には胸部のみ赤褐色のものもいる。土の中ではなく、林の朽ち(くちき)や木の根元などに巣を作るので、都心部の公園などで見かけることはほとんどない。通常見かけるのは働きアリで、巣の外では基本的に単独で行動し、行列を作るようなことはほとんどない。小さな昆虫の死骸や、アブラムシの出す蜜などを餌にする。
体長|約7~12ミリ
成虫の出現期|5~10月頃 -
シオカラトンボ トンボ科

 シオカラトンボ トンボ科
シオカラトンボ トンボ科 北海道、本州、四国、九州、沖縄に分布。平地から低山地の日当たりのよい草地や、池や沼などの水辺などに生息する。
北海道、本州、四国、九州、沖縄に分布。平地から低山地の日当たりのよい草地や、池や沼などの水辺などに生息する。
ちょっとした水たまりにも飛来し、市街地でもよく見ることのできるトンボのひとつ。春に羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)した直後は、オスもメスも地色は黄褐色で、腹部に黒い模様が入る。その後、オスだけ成熟するにしたがって体色が変わり、胸部のあたりから腹部にかけて塩が吹いたような白い粉におおわれていく。このことが和名の由来にもなっている。メスは一生にわたって体色はほぼ変わらず「麦わらとんぼ」の別名で知られる。メスは飛びながら腹部の先端を水面に打ちつけて産卵を行なう。
体長|約49~55ミリ
成虫の出現期|5~9月頃 -
オオシオカラトンボ トンボ科

 オオシオカラトンボ トンボ科
オオシオカラトンボ トンボ科 北海道、本州、四国、九州、沖縄に分布。平地から低山地の林の中や野原、水田や小川などの水辺でよく見ることができる。
北海道、本州、四国、九州、沖縄に分布。平地から低山地の林の中や野原、水田や小川などの水辺でよく見ることができる。
木陰などのある少し暗い環境を好む。シオカラトンボをひとまわり大きくしたようなトンボで、オスは成熟するにしたがって胸部のあたりから腹部にかけて同じように白い粉におおわれていくが、体色としてはシオカラトンボより青みが強い。メスも同様に黄色のまま。また、シオカラトンボの目は青緑色をしているのに対し、ほぼ黒か黒褐色。腹部が太くがっしりした体型をしている。主な餌は昆虫で、ハエやカのほか、チョウやガなども食べる。
体長|約50~60ミリ
成虫の出現期|5~11月頃 -
シオヤトンボ トンボ科

 シオヤトンボ トンボ科
シオヤトンボ トンボ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から低山地にかけて生息し、湿地帯や水田、休耕田、池や沼などの水辺でよく見ることができる。春から初夏にかけて出現するトンボで、成熟したオスの腹部が青白色になり、メスは羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)後の体色のままであることなどはシオカラトンボと同様だが、体のサイズがひとまわり小さい。また、腹部がちょっと太めであることや、翅(はね)のつけね付近がやや褐色を帯びるのもシオカラトンボとの違いになる。
北海道、本州、四国、九州に分布。平地から低山地にかけて生息し、湿地帯や水田、休耕田、池や沼などの水辺でよく見ることができる。春から初夏にかけて出現するトンボで、成熟したオスの腹部が青白色になり、メスは羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)後の体色のままであることなどはシオカラトンボと同様だが、体のサイズがひとまわり小さい。また、腹部がちょっと太めであることや、翅(はね)のつけね付近がやや褐色を帯びるのもシオカラトンボとの違いになる。
体長|約37~45ミリ
成虫の出現期|4~5月頃 -
アキアカネ トンボ科

 アキアカネ トンボ科
アキアカネ トンボ科 北海道、本州、四国、九州に分布。もっともよく見られるトンボで、古くから歌などに詠まれ親しまれてきた代表的な「赤とんぼ」だが、アキアカネは頭部や胸部は赤くならない。オスは成熟するにつれて腹部がオレンジ色から濃い赤になる。6月頃、丘陵地の水田や湿地で羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)すると、高い山へと移動し、夏の間は暑さを避けて山の上で過ごす。成熟すると9月ぐらいから低地や平地へと戻る。昔に比べて減少したが、少し都心を離れれば今も野原や空き地などで群飛(ぐんび)する光景をみることができる。よく似たナツアカネは全身が赤くなり、夏にも平地で見ることができる。主な餌はハエ、カなどの小さな昆虫類。
北海道、本州、四国、九州に分布。もっともよく見られるトンボで、古くから歌などに詠まれ親しまれてきた代表的な「赤とんぼ」だが、アキアカネは頭部や胸部は赤くならない。オスは成熟するにつれて腹部がオレンジ色から濃い赤になる。6月頃、丘陵地の水田や湿地で羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)すると、高い山へと移動し、夏の間は暑さを避けて山の上で過ごす。成熟すると9月ぐらいから低地や平地へと戻る。昔に比べて減少したが、少し都心を離れれば今も野原や空き地などで群飛(ぐんび)する光景をみることができる。よく似たナツアカネは全身が赤くなり、夏にも平地で見ることができる。主な餌はハエ、カなどの小さな昆虫類。
体長|約35~45ミリ
成虫の出現期|6~10月頃 -
ミヤマアカネ トンボ科

 ミヤマアカネ トンボ科
ミヤマアカネ トンボ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地に生息し、比較的ゆるやかな流れの川沿いや水田の周辺、池や沼などの水辺でよく見ることができる。アキアカネとともに体が真っ赤に染まるトンボで、オスは成熟すると頭部と腹部が赤く染まる。
北海道、本州、四国、九州に分布。平地から山地に生息し、比較的ゆるやかな流れの川沿いや水田の周辺、池や沼などの水辺でよく見ることができる。アキアカネとともに体が真っ赤に染まるトンボで、オスは成熟すると頭部と腹部が赤く染まる。
前後の翅(はね)の先端付近に褐色の太い帯状の模様があり、このような特徴を持つ赤とんぼはミヤマアカネだけなので判別しやすい。メスの体色はまっ赤になることはなく赤みがかかった褐色。翅の先端部に長方形の縁紋(えんもん:先端近くにある四角い斑紋)があり、オスはこれが赤く、メスは白い。小さな昆虫類が餌で、空中で捕らえて食べる。
※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。
体長|約30~40ミリ
成虫の出現期|6~9月頃 -
オニヤンマ オニヤンマ科

 オニヤンマ オニヤンマ科
オニヤンマ オニヤンマ科 北海道、本州、四国、九州、沖縄と、佐渡島、対馬、屋久島、奄美大島などに分布。日本産のトンボ類では最大種となり、大きいものは体長が11センチにもなる。生息域は平地や低地の小川や湿地、山間部の渓流などだが、ごくまれに都心部でも見かけることがある。大きな目は濃い緑色をしており、体は黒く黄色の線が一定の間隔で入っていて、非常に見栄えがする。小型の昆虫などを主食とし、これらを空中で捕食する。オスはそれぞれ一定のなわばりを持ち、その範囲内を巡回するように飛翔(ひしょう)する。メスは水面に腹部をつけたままホバリング(一定の位置で飛び続けること)し、産卵する。
北海道、本州、四国、九州、沖縄と、佐渡島、対馬、屋久島、奄美大島などに分布。日本産のトンボ類では最大種となり、大きいものは体長が11センチにもなる。生息域は平地や低地の小川や湿地、山間部の渓流などだが、ごくまれに都心部でも見かけることがある。大きな目は濃い緑色をしており、体は黒く黄色の線が一定の間隔で入っていて、非常に見栄えがする。小型の昆虫などを主食とし、これらを空中で捕食する。オスはそれぞれ一定のなわばりを持ち、その範囲内を巡回するように飛翔(ひしょう)する。メスは水面に腹部をつけたままホバリング(一定の位置で飛び続けること)し、産卵する。
体長|約90~100ミリ
成虫の出現期|6~10月頃 -
アサヒナカワトンボ カワトンボ科

 アサヒナカワトンボ カワトンボ科
アサヒナカワトンボ カワトンボ科 北海道、本州、四国、九州と幅広いエリアに分布。カワトンボの仲間はイトトンボを大きくしたような体つきをしており、その名前が示すとおり、平地から山地の清流や山間の渓流を主な生息域にしている。前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)と後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)がほぼ同じ形で、ひらひらと優雅に飛びまわる。 翅(はね)の色にはかなり個体差や地域差があって、赤褐色が強いものから、薄くオレンジ色がかったもの、無色透明のものまでいろいろ。体色は、成虫になったばかりのころはメタリック系の光沢がある緑色をしているが、成熟するにつれて白く粉を吹いたようになっていく。主な餌となるのは、水辺にいる小型昆虫。
北海道、本州、四国、九州と幅広いエリアに分布。カワトンボの仲間はイトトンボを大きくしたような体つきをしており、その名前が示すとおり、平地から山地の清流や山間の渓流を主な生息域にしている。前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)と後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)がほぼ同じ形で、ひらひらと優雅に飛びまわる。 翅(はね)の色にはかなり個体差や地域差があって、赤褐色が強いものから、薄くオレンジ色がかったもの、無色透明のものまでいろいろ。体色は、成虫になったばかりのころはメタリック系の光沢がある緑色をしているが、成熟するにつれて白く粉を吹いたようになっていく。主な餌となるのは、水辺にいる小型昆虫。
体長|約55~60ミリ
成虫の出現期|4~8月頃 -
ミヤマカワトンボ カワトンボ科

 ミヤマカワトンボ カワトンボ科
ミヤマカワトンボ カワトンボ科 北海道、本州、四国、九州に分布。低地から山地にかけての清流や渓流などを主なすみかとしている。日本産のカワトンボのなかでは最大。主な餌は小型の昆虫類。半透明な深みのある茶色の翅(はね)を持ち、水辺をゆるやかに飛び回る姿は、メタリックグリーンの腹部と相まって非常に優雅にみえる。メスは翅の先端に近いところに白の縁紋(えんもん:先端近くにある四角い斑紋)が入り、腹部の色は褐色系。オスはそれぞれなわばりをもっていて、そこにやってきたメスと交尾をする。
北海道、本州、四国、九州に分布。低地から山地にかけての清流や渓流などを主なすみかとしている。日本産のカワトンボのなかでは最大。主な餌は小型の昆虫類。半透明な深みのある茶色の翅(はね)を持ち、水辺をゆるやかに飛び回る姿は、メタリックグリーンの腹部と相まって非常に優雅にみえる。メスは翅の先端に近いところに白の縁紋(えんもん:先端近くにある四角い斑紋)が入り、腹部の色は褐色系。オスはそれぞれなわばりをもっていて、そこにやってきたメスと交尾をする。
メスは水中で産卵することもあり、翅や体表にできる空気の膜を利用し、1時間近く潜っていることができる。
※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。
体長|約60~65ミリ
成虫の出現期|5~9月頃 -
ダビドサナエ サナエトンボ科

 ダビドサナエ サナエトンボ科
ダビドサナエ サナエトンボ科 本州、四国、九州と、対馬などに分布。丘陵地から山間部にある渓流など、河川の中流から上流域の周辺に生息する。名前は19世紀のフランス人動物学者のダビド氏に捧げられたもの。体色は黒く、胸部から腹部にかけて黄色の模様が入る。胸部側面に大きめの黄斑が3つ並び、オス・メスとも前脚のつけねが黄色い。高尾山周辺の流れのある川辺では比較的ふつうにいるトンボで、姿を現しはじめるのは4月から5月にかけて。オスはなわばりを持ち、石の上にとまって周囲を警戒し、交尾相手となるメスを待つ。メスは単独で空中をホバリングしながら、水面に卵を産みおとす。
本州、四国、九州と、対馬などに分布。丘陵地から山間部にある渓流など、河川の中流から上流域の周辺に生息する。名前は19世紀のフランス人動物学者のダビド氏に捧げられたもの。体色は黒く、胸部から腹部にかけて黄色の模様が入る。胸部側面に大きめの黄斑が3つ並び、オス・メスとも前脚のつけねが黄色い。高尾山周辺の流れのある川辺では比較的ふつうにいるトンボで、姿を現しはじめるのは4月から5月にかけて。オスはなわばりを持ち、石の上にとまって周囲を警戒し、交尾相手となるメスを待つ。メスは単独で空中をホバリングしながら、水面に卵を産みおとす。
体長|約40~50ミリ
成虫の出現期|4~7月頃 -
クロサナエ サナエトンボ科

 クロサナエ サナエトンボ科
クロサナエ サナエトンボ科 本州、四国、九州に分布。低地から山地の源流に近い渓流や沢沿いなど、河川上流域のきれいな川に主に生息している。別種のダビドサナエと非常に似ているが、クロサナエは名前のとおり、オスの腹部がほとんど黒で、側面にも黄色の模様が入らないことで区別できる。また、胸部側面の黄斑のうち、中央のものが小さいこと、前脚のつけねに黄斑がないことなどで区別できる。メスは単独で空中をホバリング(一定の位置で飛び続けること)しながら、水辺のコケや丈の低い植物が生い茂る場所に卵を産みおとす。主な餌は小さな昆虫類。4月下旬頃から羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)しはじめて、夏ぐらいまで姿を見ることができる。
本州、四国、九州に分布。低地から山地の源流に近い渓流や沢沿いなど、河川上流域のきれいな川に主に生息している。別種のダビドサナエと非常に似ているが、クロサナエは名前のとおり、オスの腹部がほとんど黒で、側面にも黄色の模様が入らないことで区別できる。また、胸部側面の黄斑のうち、中央のものが小さいこと、前脚のつけねに黄斑がないことなどで区別できる。メスは単独で空中をホバリング(一定の位置で飛び続けること)しながら、水辺のコケや丈の低い植物が生い茂る場所に卵を産みおとす。主な餌は小さな昆虫類。4月下旬頃から羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)しはじめて、夏ぐらいまで姿を見ることができる。
体長|約40~50ミリ
成虫の出現期|4~7月頃 -
コオニヤンマ サナエトンボ科

 コオニヤンマ サナエトンボ科
コオニヤンマ サナエトンボ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から低山地の小川や川沿い、水辺のそばの草むらなどに生息し、河原の石や木の枝に 翅(はね)を平らに広げてよくとまっている。5月下旬頃から羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)して姿を現し、8月頃まで見ることができる。名前は「小さなオニヤンマ」を意味するが、実はサナエトンボの仲間。サナエトンボのなかでは最大種となり、オニヤンマとは体に対して頭が小さいこと、後ろ脚が非常に長いことなどで区別がつく。ほかのトンボやセミなどさまざまな生きた昆虫を捕獲して食べる。オスはなわばりを持ち、石の上や樹木の枝先などに静止しながら周囲を警戒し、ときおりパトロールする。
北海道、本州、四国、九州に分布。平地から低山地の小川や川沿い、水辺のそばの草むらなどに生息し、河原の石や木の枝に 翅(はね)を平らに広げてよくとまっている。5月下旬頃から羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)して姿を現し、8月頃まで見ることができる。名前は「小さなオニヤンマ」を意味するが、実はサナエトンボの仲間。サナエトンボのなかでは最大種となり、オニヤンマとは体に対して頭が小さいこと、後ろ脚が非常に長いことなどで区別がつく。ほかのトンボやセミなどさまざまな生きた昆虫を捕獲して食べる。オスはなわばりを持ち、石の上や樹木の枝先などに静止しながら周囲を警戒し、ときおりパトロールする。
体長|約80~90ミリ
成虫の出現期|5~8月頃 -
ムカシトンボ ムカシトンボ科

 ムカシトンボ ムカシトンボ科
ムカシトンボ ムカシトンボ科 北海道、本州、四国、九州に分布。生殖器など多くの部分に原始的な特徴をとどめているため、「生きた化石」として世界的に知られる。ムカシトンボ科で現存するのは日本産の本種のほかに、ヒマラヤに1種と中国北東部に2種がいるのみ。体はサナエトンボに似るが、前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)と後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の形がほとんど同じという、イトトンボのような特徴を持つ。河川の上流域や樹林に囲まれた渓流に生息しており、ハエやカなどの小型の昆虫を餌にする。メスは水辺の植物の茎などに産卵し、ふ化した幼虫は渓流中の石の隙間などにすむ。水中で7~8年を経た後上陸し、1か月ほど水辺ですごしてから羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)して成虫となる。
北海道、本州、四国、九州に分布。生殖器など多くの部分に原始的な特徴をとどめているため、「生きた化石」として世界的に知られる。ムカシトンボ科で現存するのは日本産の本種のほかに、ヒマラヤに1種と中国北東部に2種がいるのみ。体はサナエトンボに似るが、前翅(ぜんし:二対ある翅のうち前方にあるもの)と後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)の形がほとんど同じという、イトトンボのような特徴を持つ。河川の上流域や樹林に囲まれた渓流に生息しており、ハエやカなどの小型の昆虫を餌にする。メスは水辺の植物の茎などに産卵し、ふ化した幼虫は渓流中の石の隙間などにすむ。水中で7~8年を経た後上陸し、1か月ほど水辺ですごしてから羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)して成虫となる。
体長|約50~60ミリ
成虫の出現期|5月頃 -
アブラゼミ セミ科

 アブラゼミ セミ科
アブラゼミ セミ科 北海道、本州、四国、九州と、対馬、屋久島などに分布。平地から山地の雑木林や樹林に主に生息し、木の幹にとまって樹液を吸う。大木のある公園やナシなどの果樹園でもよく見られ、全国で最もよく見られるセミのひとつ。セミの仲間は鳴くのはオスのみで、アブラゼミは「ジュイー」「ジュジュジュジュー」といった声でよく鳴く。この鳴き声が、油でものを揚げる音に似ていることが名前の由来とされている。 翅(はね)は全体が不透明な茶褐色で、ところどころに濃淡の模様が入る。メスは樹皮に卵を産み、約1年でふ化する。幼虫は地中で樹木の根から樹液を吸って生活し、6年から7年を経て地上へ上がり、羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)して成虫となる。
北海道、本州、四国、九州と、対馬、屋久島などに分布。平地から山地の雑木林や樹林に主に生息し、木の幹にとまって樹液を吸う。大木のある公園やナシなどの果樹園でもよく見られ、全国で最もよく見られるセミのひとつ。セミの仲間は鳴くのはオスのみで、アブラゼミは「ジュイー」「ジュジュジュジュー」といった声でよく鳴く。この鳴き声が、油でものを揚げる音に似ていることが名前の由来とされている。 翅(はね)は全体が不透明な茶褐色で、ところどころに濃淡の模様が入る。メスは樹皮に卵を産み、約1年でふ化する。幼虫は地中で樹木の根から樹液を吸って生活し、6年から7年を経て地上へ上がり、羽化(うか:成虫になるための最後の脱皮)して成虫となる。
全長(頭から翅の先まで)|約50~60ミリ
成虫の出現期|7~9月頃 -
ツクツクボウシ セミ科

 ツクツクボウシ セミ科
ツクツクボウシ セミ科 北海道、本州、四国、九州と、対馬、屋久島などの島に分布。平地から低山地の樹林や雑木林などに生息する。都市部の公園や街路樹などでも見ることができる。さまざまな樹木に飛来して、樹液を吸う。8月から9月頃にかけてもっともよく出現する。
北海道、本州、四国、九州と、対馬、屋久島などの島に分布。平地から低山地の樹林や雑木林などに生息する。都市部の公園や街路樹などでも見ることができる。さまざまな樹木に飛来して、樹液を吸う。8月から9月頃にかけてもっともよく出現する。
名前の由来ともなっている「オーシーツクツク」という独特の抑揚のついた鳴き声が印象的。午前、午後とあまり時間を問わずに鳴く。体色は黄褐色から黒色でところどころに緑色の模様が入る。オスとメスは、体の大きさはさほど変わらないが、オスは腹部のほとんどが空洞で丸みをおびており、メスは先端に産卵管があるためとがっている。
全長|約45ミリ前後
成虫の出現期|7~10月頃 -
ヒグラシ セミ科

 ヒグラシ セミ科
ヒグラシ セミ科 北海道南部、本州、四国、九州と、屋久島などに分布。平地から低山地の樹林に主に生息する。比較的早い時期から出現する種類で、6月ぐらいから姿を現しはじめ、最盛期は7月になる。「日暮らし」の名のように、夕闇迫る日暮れ時に金属的な響きのある「ヒヒヒヒヒ」といった声で鳴くが、文字では「カナカナ」と表現されることが多い。あたりがまだ薄暗い早朝や、曇っていれば日中でも鳴くことがある。体色は個体差があるが、地色は茶褐色でところどころに緑と黒の模様を持つものが多い。オスは腹部が大きいがほとんど空洞で、メスは先端がとがる。体に白い綿のようなものがついていることがあるが、これはセミヤドリガというガの幼虫の寄生によるもの。
北海道南部、本州、四国、九州と、屋久島などに分布。平地から低山地の樹林に主に生息する。比較的早い時期から出現する種類で、6月ぐらいから姿を現しはじめ、最盛期は7月になる。「日暮らし」の名のように、夕闇迫る日暮れ時に金属的な響きのある「ヒヒヒヒヒ」といった声で鳴くが、文字では「カナカナ」と表現されることが多い。あたりがまだ薄暗い早朝や、曇っていれば日中でも鳴くことがある。体色は個体差があるが、地色は茶褐色でところどころに緑と黒の模様を持つものが多い。オスは腹部が大きいがほとんど空洞で、メスは先端がとがる。体に白い綿のようなものがついていることがあるが、これはセミヤドリガというガの幼虫の寄生によるもの。
全長|約40~50ミリ
成虫の出現期|6~9月頃 -
ミンミンゼミ セミ科

 ミンミンゼミ セミ科
ミンミンゼミ セミ科 北海道南部、本州、四国、九州と、対馬に分布。平地から山地の樹林に主に生息している。関東ではアブラゼミとならんでもっともよく見ることのできるセミで、都会の街路樹や公園の樹木にも多い。7月中旬頃から姿を現し、名前のとおりに「ミーン、ミン、ミン、ミン」と大きな声で鳴く。体は黒色で緑色のまだら模様を持ち、背面中央は白く粉をふいたようになる。まれに全体が黒色の個体や、ミカド型と呼ばれる全体が緑色をした個体もいる。翅(はね)は透明で胴体よりも倍近く長い。ほかのセミと同じくとがった口を木に刺して汁を吸う。卵からふ化した幼虫は成虫になるまでに6年かかる。
北海道南部、本州、四国、九州と、対馬に分布。平地から山地の樹林に主に生息している。関東ではアブラゼミとならんでもっともよく見ることのできるセミで、都会の街路樹や公園の樹木にも多い。7月中旬頃から姿を現し、名前のとおりに「ミーン、ミン、ミン、ミン」と大きな声で鳴く。体は黒色で緑色のまだら模様を持ち、背面中央は白く粉をふいたようになる。まれに全体が黒色の個体や、ミカド型と呼ばれる全体が緑色をした個体もいる。翅(はね)は透明で胴体よりも倍近く長い。ほかのセミと同じくとがった口を木に刺して汁を吸う。卵からふ化した幼虫は成虫になるまでに6年かかる。
全長|約55~63ミリ
成虫の出現期|7~9月頃 -
エサキモンキツノカメムシ ツノカメムシ科

 エサキモンキツノカメムシ ツノカメムシ科
エサキモンキツノカメムシ ツノカメムシ科 本州、四国、九州と、対馬、奄美大島などに分布。低地から山地の雑木林や草地などに生息する。背面は茶褐色で、前翅(ぜんし:二対ある翅(はね)のうち前方にあるもの)からはみ出た腹部や脚は緑から黄緑色。胸部の両端がとがるツノカメムシの仲間で、背面上部にあるハート形のような黄白色の紋がよく目立つ。エサキは日本の昆虫学者、江崎悌三博士に捧げられたもの。ミズキ、ハゼノキ、ウド、カラスザンショウなどの樹の上にいることが多く、これらの木の汁を吸う。メスは産んだ卵を守る習性があり、ミズキなどの葉の裏などに卵を産みつけるとそれを抱え込むようにして、ふ化後もしばらく幼虫を外敵から守り続ける。
本州、四国、九州と、対馬、奄美大島などに分布。低地から山地の雑木林や草地などに生息する。背面は茶褐色で、前翅(ぜんし:二対ある翅(はね)のうち前方にあるもの)からはみ出た腹部や脚は緑から黄緑色。胸部の両端がとがるツノカメムシの仲間で、背面上部にあるハート形のような黄白色の紋がよく目立つ。エサキは日本の昆虫学者、江崎悌三博士に捧げられたもの。ミズキ、ハゼノキ、ウド、カラスザンショウなどの樹の上にいることが多く、これらの木の汁を吸う。メスは産んだ卵を守る習性があり、ミズキなどの葉の裏などに卵を産みつけるとそれを抱え込むようにして、ふ化後もしばらく幼虫を外敵から守り続ける。
※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。
体長|約10~12ミリ
成虫の出現期|5~10月頃 -
アカスジキンカメムシ キンカメムシ科

 アカスジキンカメムシ キンカメムシ科
アカスジキンカメムシ キンカメムシ科 本州、四国、九州に分布。山地の雑木林に生息する。体色は金属的な光沢のある緑色で、名前のとおり、銅色に近い赤のすじ模様が入る。カメムシのなかでも美しい種類としてよく知られる。幼虫は白地に黒い模様が入り、カラフルな成虫とはまったく違った姿をしていて、模様が人の笑い顔のように見えるものもいる。6月頃に成虫になり、樹木の幹や葉の上などにとまっていることが多い。キブシ、ハンノキ、ミズキ、スギ、ヒノキなど、さまざまな樹木から発見され、果実などの汁を吸う。幼虫も木や果実、葉の汁を吸う。
本州、四国、九州に分布。山地の雑木林に生息する。体色は金属的な光沢のある緑色で、名前のとおり、銅色に近い赤のすじ模様が入る。カメムシのなかでも美しい種類としてよく知られる。幼虫は白地に黒い模様が入り、カラフルな成虫とはまったく違った姿をしていて、模様が人の笑い顔のように見えるものもいる。6月頃に成虫になり、樹木の幹や葉の上などにとまっていることが多い。キブシ、ハンノキ、ミズキ、スギ、ヒノキなど、さまざまな樹木から発見され、果実などの汁を吸う。幼虫も木や果実、葉の汁を吸う。
体長|約17~20ミリ
季節|6~8月頃 -
ツマグロオオヨコバイ ヨコバイ科

 ツマグロオオヨコバイ ヨコバイ科
ツマグロオオヨコバイ ヨコバイ科 本州、四国、九州、沖縄に分布。平地から低山地の雑木林や、その周辺の緑地や農地をはじめ、庭や市街地の花壇などでも目にすることができる。体色は緑から黄緑色で、頭部と胸部にいくつかの黒い点が並び、翅(はね)の下端部分も黒く染まっている。名前の「ツマグロ」は、これにちなむ。日中は草木の葉の裏などにいて、夜になると飛んで移動し、灯火にも集まる。クワやキイチゴ、ブドウ類などの汁を吸うが、食草(主な餌としている植物)はさまざまで、農作物に被害をもたらすことも多い。「ヨコバイ」の名が示すとおり、危険を感じると素早く横に動いて、葉の裏側などに身を隠す。
本州、四国、九州、沖縄に分布。平地から低山地の雑木林や、その周辺の緑地や農地をはじめ、庭や市街地の花壇などでも目にすることができる。体色は緑から黄緑色で、頭部と胸部にいくつかの黒い点が並び、翅(はね)の下端部分も黒く染まっている。名前の「ツマグロ」は、これにちなむ。日中は草木の葉の裏などにいて、夜になると飛んで移動し、灯火にも集まる。クワやキイチゴ、ブドウ類などの汁を吸うが、食草(主な餌としている植物)はさまざまで、農作物に被害をもたらすことも多い。「ヨコバイ」の名が示すとおり、危険を感じると素早く横に動いて、葉の裏側などに身を隠す。
体長|約6~8ミリ
成虫の出現期|3~11月頃 -
アオバハゴロモ アオバハゴロモ科

 アオバハゴロモ アオバハゴロモ科
アオバハゴロモ アオバハゴロモ科 本州、四国、九州と、南西諸島に分布。平地から山地の雑木林や緑地、花だんなどに生息する。全身がきれいなうす緑色で、三角形の 前翅(ぜんし:二対ある翅(はね)のうち前方にあるもの)はピンク色にふちどられ、「羽衣(はごろも )」という名がよく似合う。後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)は白色で、ふだんは前翅の下に隠されている。
本州、四国、九州と、南西諸島に分布。平地から山地の雑木林や緑地、花だんなどに生息する。全身がきれいなうす緑色で、三角形の 前翅(ぜんし:二対ある翅(はね)のうち前方にあるもの)はピンク色にふちどられ、「羽衣(はごろも )」という名がよく似合う。後翅(こうし:二対ある翅のうち後方にあるもの)は白色で、ふだんは前翅の下に隠されている。
同じハゴロモ類でもベッコウハゴロモなどは翅を開いて止まるが、アオバハゴロモは翅を屋根型に立ててとまる。成虫は7月中~下旬ぐらいから姿を見せはじめ、植物の茎に何匹も連なってとまっているところをよく見かける。さわるといきおいよく跳ねて逃げる。幼虫・成虫ともに、クワやミカン類など、様々な草木の汁を吸う。初夏の5月頃、卵からふ化した幼虫は、白い綿状の分泌物で体をおおい、外敵から身を守る。
体長|約9~11ミリ
季節|7~10月頃 -
ベッコウハゴロモ ハゴロモ科

 ベッコウハゴロモ ハゴロモ科
ベッコウハゴロモ ハゴロモ科 本州、四国、九州、沖縄と、屋久島、対馬などの島に分布。平地から低山地にある日当たりのいい雑木林や、開けた草むらなどに棲む。植物のあるところなら市街地でも見ることができるハゴロモの仲間。個体差はあるが主に黄褐色から茶褐色で、翅(はね)には太い帯状の半透明な部分がある。先端近くに黒い斑紋があり、翅を開いてとまっているところはガのようにも見える。ミカンをはじめとした柑橘類、クズなどのマメ科、ヤマノイモ、ウツギといった植物の茎に針のような口を刺して、汁を吸う。幼虫には褐色と白のまだら模様があり、腹部先端に淡い黄色の綿毛のようなものをつけている。
本州、四国、九州、沖縄と、屋久島、対馬などの島に分布。平地から低山地にある日当たりのいい雑木林や、開けた草むらなどに棲む。植物のあるところなら市街地でも見ることができるハゴロモの仲間。個体差はあるが主に黄褐色から茶褐色で、翅(はね)には太い帯状の半透明な部分がある。先端近くに黒い斑紋があり、翅を開いてとまっているところはガのようにも見える。ミカンをはじめとした柑橘類、クズなどのマメ科、ヤマノイモ、ウツギといった植物の茎に針のような口を刺して、汁を吸う。幼虫には褐色と白のまだら模様があり、腹部先端に淡い黄色の綿毛のようなものをつけている。
※ここでは、「斑点」は点状の模様、「斑紋」はある程度大きな模様を指しています。
体長|約6~8ミリ
成虫の出現期|7~9月頃 -
ヤマトフキバッタ バッタ科

 ヤマトフキバッタ バッタ科
ヤマトフキバッタ バッタ科 本州の東北から近畿地方に分布。低地から低山地、山地までに生息しており、森林周辺の緑地や樹林などの草むらをすみかにする。イナゴによく似るが、成虫でも翅(はね)が胴体の半分の長さもなく、飛ぶことができない。後ろ脚を使っての跳躍は得意だが、あまり動きは活発でなく活動範囲も狭い。名前はフキの葉を好むとされたことによるが、ほかにもクズなど様々な草木の葉を食べる。成虫は7月下旬頃から姿を現す。体色などでオスとメスの違いはないが、オスよりもメスが大きい。また、オスは下腹部に突起がある。フキバッタの仲間は似た種類が多く、野外では、外見だけで見分けることは難しい。
本州の東北から近畿地方に分布。低地から低山地、山地までに生息しており、森林周辺の緑地や樹林などの草むらをすみかにする。イナゴによく似るが、成虫でも翅(はね)が胴体の半分の長さもなく、飛ぶことができない。後ろ脚を使っての跳躍は得意だが、あまり動きは活発でなく活動範囲も狭い。名前はフキの葉を好むとされたことによるが、ほかにもクズなど様々な草木の葉を食べる。成虫は7月下旬頃から姿を現す。体色などでオスとメスの違いはないが、オスよりもメスが大きい。また、オスは下腹部に突起がある。フキバッタの仲間は似た種類が多く、野外では、外見だけで見分けることは難しい。
体長|約22~30ミリ
成虫の出現期|7~9月頃 -
ヤブキリ キリギリス科

 ヤブキリ キリギリス科
ヤブキリ キリギリス科 本州、四国、九州に分布。平地から山地のやぶや、雑木林の周辺の草むらなどの、比較的高い場所を主なすみかにするキリギリスの仲間。体全体は緑色で、背面が褐色になり、一直線のすじが入ったようになっている。翅(はね)は体と同じ緑色。成虫は6月下旬頃から姿を現しはじめ、「ジー、ジー、ジー、ジー」という独特の鳴き声を響かす。幼虫は草の葉や花の花粉などを主食とする草食性だが、成長するにつれて肉食傾向が強くなり、成虫はときに自分と変わらない大きさの昆虫をつかまえて食べることもある。脚には虫を捕獲するのに適した鋭いトゲをいくつももっている。
本州、四国、九州に分布。平地から山地のやぶや、雑木林の周辺の草むらなどの、比較的高い場所を主なすみかにするキリギリスの仲間。体全体は緑色で、背面が褐色になり、一直線のすじが入ったようになっている。翅(はね)は体と同じ緑色。成虫は6月下旬頃から姿を現しはじめ、「ジー、ジー、ジー、ジー」という独特の鳴き声を響かす。幼虫は草の葉や花の花粉などを主食とする草食性だが、成長するにつれて肉食傾向が強くなり、成虫はときに自分と変わらない大きさの昆虫をつかまえて食べることもある。脚には虫を捕獲するのに適した鋭いトゲをいくつももっている。
体長|約30~40ミリ
成虫の出現期|6~9月頃 -
カンタン コオロギ科

 カンタン コオロギ科
カンタン コオロギ科 北海道、本州、四国、九州に分布。平地から低山地の林に近い草むらや、緑地などにすんでいる。体は薄い緑色で長細く、バッタに近い印象だが、コオロギの仲間である。触角は長く、体長の3倍ほどになる。クズ、ヨモギなどをよく食べることから、これらの植物が生える草むらの葉の裏などにいることが多い。アブラムシなど小さな虫も食べる。秋に鳴く虫としてよく知られ、清涼感のある「ルルルルル…」といった鳴き声は「鳴く虫の女王」と称されるほど。和歌の秋の季語にもなっている。
北海道、本州、四国、九州に分布。平地から低山地の林に近い草むらや、緑地などにすんでいる。体は薄い緑色で長細く、バッタに近い印象だが、コオロギの仲間である。触角は長く、体長の3倍ほどになる。クズ、ヨモギなどをよく食べることから、これらの植物が生える草むらの葉の裏などにいることが多い。アブラムシなど小さな虫も食べる。秋に鳴く虫としてよく知られ、清涼感のある「ルルルルル…」といった鳴き声は「鳴く虫の女王」と称されるほど。和歌の秋の季語にもなっている。
体長|約15ミリ前後
成虫の出現期|8~11月頃 -
コロギス コロギス科

 コロギス コロギス科
コロギス コロギス科 本州、四国、九州に分布。平地から山地の雑木林や緑地に生息している。コオロギとキリギリスのちょうど中間的な特徴を持つことからこの名があるが、夜行性ということもあり、一般にはあまり知られていない。コオロギやキリギリスにある発音器官はもたないので、鳴くこともない。全身はつやのある黄緑色で前翅(ぜんし:二対ある翅(はね)のうち前方にあるもの)の背面が黄褐色をしている。触角が非常に長く、体長の3倍以上にもなる。口から粘着性のある糸を出し、それを使って葉を重ね合わせた巣をつくり、日中はそこで過ごすことが多い。夜になると活発に動き出し、樹上などで昆虫を捕らえて食べる。
本州、四国、九州に分布。平地から山地の雑木林や緑地に生息している。コオロギとキリギリスのちょうど中間的な特徴を持つことからこの名があるが、夜行性ということもあり、一般にはあまり知られていない。コオロギやキリギリスにある発音器官はもたないので、鳴くこともない。全身はつやのある黄緑色で前翅(ぜんし:二対ある翅(はね)のうち前方にあるもの)の背面が黄褐色をしている。触角が非常に長く、体長の3倍以上にもなる。口から粘着性のある糸を出し、それを使って葉を重ね合わせた巣をつくり、日中はそこで過ごすことが多い。夜になると活発に動き出し、樹上などで昆虫を捕らえて食べる。
樹液や花の蜜も好む。
体長|約30~40ミリ
成虫の出現期|7~9月頃
